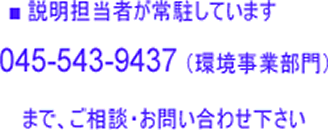1.オゾンとは
地球の大気中には酸素があります。
その酸素は2つの酸素原子からできた分子(O2)で、オゾンはその酸素分子に酸素原子が1つ加わった、
3つの酸素原子からなる分子(O3)です。
オゾンは40数億年前から存在する、比重1.6の気体で、雷の放電や太陽の紫外線などによって生成され、
紫外線と共に地球環境の衛生管理にオゾンが大きな役割を果たしてきました。
有害波長の紫外線から人間を守ってくれているオゾン層では10〜20ppm濃度(=1g中に100万分の1g=1ppm)で、
通常環境の大気中には無意識量(約0.005ppm)でオゾンは存在していますが、オゾンは特に海岸(0.03〜0.06ppm)、
森林や高原(0.05〜0.1ppm)の空気中に多く含まれています。そのため、微量なオゾンと人間の共存は、すでに
長い期間の安全テストを済ませていると言えます。
オゾンの特徴は強い酸化力を持つことで、工業的には無声放電、電解、沿面放電、紫外線照射等の方法で
濃度の高いオゾンを発生させます。その優れた酸化力を利用して、水や空気の浄化・殺菌、脱色、有機物除去等
広い分野にわたり私たちの生活や環境の保護に役立っています。
自然発生するオゾンは、主に太陽光線に含まれる紫外線が酸素に触れるか、また突発的な落雷などの自然放電
による空気分解時にも、酸素原子3個が結びついて発生します。(突発的な放電分解ではNOxも発生)
酸素原子が3個の状態は、酸素分子(酸素原子2個)に不安定な酸素原子1個が結びついているので、
この不安定な酸素原子が他の分子などに結び付き、有機化合物を二酸化炭素と水に酸化分解します。
細菌レベルにおいては細胞膜を破壊してしまうので、細菌は乾燥死します。

2.オゾンによる殺菌・脱臭について
オゾンは1840年、ドイツの化学者シェーンバインにより発見されました。科学的に認知されたのも1840年代で、
その殺菌作用は1873年には判明しており、酸化・殺菌・悪臭除去の目的でオゾンが実用され始めてから
100年以上の歴史を持ちます。
しかしオゾンおよびオゾン水が食品に対する「抗微生物剤」として正式認可を受けたのは
アメリカでも21世紀(2001年6月26日公布)からで、ヨーロッパでは歯科治療での傷の治りの促進にオゾンが
注目され、殺菌と生組織活性化に気体がかけられるなど、日常の中で有効にオゾンが活かされていますが、
政治と業界団体の結びつきが強いアメリカや日本では、むしろ有害性のリスクを抱えた塩素が安価であった
こともあり重用され、オゾンの産業分野での利用すらも遅れ、一般にも認知に至っていません。
しかしオゾンによる殺菌殺菌脱臭には、以下のようなメリットがあります。
・塩素と比較して2倍(空気中)〜6倍(水中)程度の殺菌力、3000倍以上の殺菌スピードを持ちます。
・塩素は細菌の細胞膜に浸透して新たな耐性菌を発生させる危険性もありますが、オゾンは細菌の細胞膜を破壊して
乾燥死させるので、耐性菌を発生させることも無く、二次汚染の心配がありません。
・ヒ素/ホルマリン/塩素等は残留(ホルマリンで4^5日)するため、頻繁な使用では蓄積され使用後も処理を要しますが、
オゾンは酸素に戻るため廃棄などの処理が必要がありません。
あらゆる分子の中でオゾンのみが酸素に戻る性質を持っており、そのオゾンの酸素に戻る還元速度は早く、
密閉放置で10数時間、換気すれば分単位で検知不能な濃度になります。
オゾンは微臭性で濃度を自覚できるため、世界でオゾンによる職場事故の報告例はありません。
小さな虫やネズミなどはオゾンを嫌い姿を消します。またフェロモンが分解消臭されて交尾〜繁殖できなくなります。

3.オゾンの留意点
*オゾンの酸化作用により、有機素材(天然ゴムなど)は劣化します。
また長期の使用では雨水と同様に金属を酸化します。
・極端な濃度では塩や酢や酒も有害なように、オゾンも濃度を選ぶ必要があります。
オゾンの人体への有害性については、『60度のお風呂の有害性・危険性』を訴えるのに等しく、
その危険な状態より、はるか手前で風呂なら火を止めたりあがるのと同様に、濃いオゾンの
ニオイなどで自然に人は換気するなどするので、オゾン事故の報告は1件もありません。
・光化学オキシダントとオゾンの混同も間違いです。原因の一つは平成8年の環境省告示にあり、
「観測されたオゾン濃度指示値を光化学オキシダントの濃度としてもよい」という発表が、
「光化学オキシダント濃度=オゾンの濃度」と誤用され「オゾン=光化学オキシダント」という誤解に結び付いています。
オゾンは酸素原子の集まりで、光化学オキシダントは排気ガス中の有機物成分に光が作用して生じたエアロゾルで、
オゾンと光化学スモッグは、まったくの別物です。
*日本オゾン協会理事の、杉光英俊 徳山大学学長は、以下のようにコメント(抜粋)されています。
「 光化学スモッグがはじめて問題になったのは1955年7月のロサンゼルスである。快晴にもかかわらず視界がぼやけ、
目や喉の不快感を訴える人が急増した。後の研究で、原因は自動車の排気ガスと紫外線によって引き起こされた
いわゆる光化学スモッグであることがわかった。 日本では、1970年7月に杉並区の高校で女生徒が目の痛みや頭痛を
訴えて倒れ、病院に運び込まれる事件が起きた。その後日本の各地で同様の被害が報告されている。しかし、オゾンは
名前が「臭い」というギリシャ語に由来するほど臭いが強いが、これまでに臭いを感じたという報告は見られない。
臭いが感知できない濃度で障害が発生することはオゾンに携わってきた者には極めて考えにくい。」

4. オゾンの生成方法
(1) 太陽の紫外線による酸素分解 (オゾン層、海岸地帯など)
(2) 落雷などの激しい放電分解
自然発生するオゾンは、主に太陽光線に含まれる紫外線が酸素に触れるか、
落雷などの自然放電による空気分解(NOxも発生)時に酸素原子3個が結びついて発生します。
酸素分子が3個の状態は、酸素(酸素原子2個)に不安定な酸素原子1個が結びついているので、
この不安定な酸素原子が他の分子に結び付き、有機化合物を二酸化炭素と水に酸化分解します。
細菌レベルにおいては細胞膜を破壊してしまうので、細菌は乾燥死します。
呼吸器疾患などの長期療養に使われるサナトリウムが高原や海岸に多く作られたのも、
それらの場所では微量オゾンによって衛生的な空気が得られたことが、場所選定のポイントになっています。
この(1)の原理により、紫外線によるオゾン環境を作り出すのが紫外線オゾン装置です。
・紫外線オゾン装置は、185nm/254nm同時発生ランプ*を使用します。
・185nm/254nm紫外線は、どちらも窒素を分解しないため、有害な窒素酸化物(NOx)を含みません。
先端の技術開発に欠かせない光洗浄/光改質や光酸化技術も、
この紫外線オゾン技術が基礎になっています。 >
光洗浄/光改質装置 光酸化(水処理)装置
[*185nm/254nm同時発生ランプ(オゾンランプ)]:大阪府新技術支援により開発(特許取得)
185nm波長の紫外線=オゾン発生効果が高い
254nm波長の紫外線=殺菌と、オゾン活性化 (素早く効果、素早く消える)
この2波長の特性を組み合わせ、純粋オゾンによる衛生的な環境を創ります。 |
紫外線以外のオゾン生成方式では、前述(2)の「放電によるスパーク」を利用します。
この方式では、空気中の窒素が分解されてNOxに変わり、これは少量でも有害です。
また「穏やかな放電・スパーク」は実現不可なので、大気を利用する放電方式の装置から出る気体は、
「大量のNOxに、オゾンが混ざったもの」を高濃度にした雑気体にしかなりません。
このように大気を放電方式で分解して得た雑気体をオゾンと誤認しているケースが多く、
その場合「オゾンに大量のNOxが混ざったニオイ=オゾン臭」と誤認されています。
「放電によるスパーク」式装置は、コイル等を使って放電させるだけなので簡単・安価に作れますが、
この方式で純粋なオゾンを得るにはIHIのように、密閉箱で酸素を分解して高濃度なオゾンを作る方式か、
タムラテコのように空気中の酸素と窒素を分けて、酸素濃度をあげてNOxを防止するしかありません。
通常の窒素除去フィルターは、網状にした触媒に触れた窒素のみを除去し、大半の窒素は網目を素通りします。
紫外線ランプ方式やタムラテコなどの脱窒方式以外の「オゾン発生器」では、窒素酸化物の発生に注意が必要で、
目に見えず健康を害するNOxを、発生させない構造になっているか見極める必要があります。
前出のタムラテコでは、オゾン水(オゾンを水に溶かしたもので、20分程度は殺菌力が持続します)を作る装置には、
紫外線オゾン方式で発生させることのできるオゾンでは濃度が足りないため、放電方式のオゾン装置に組み合わせる
ための、機能の優れた脱窒カートリッジの開発を行い、その脱窒カートリッジを空気用装置にも応用して高濃度用の
オゾン生成装置を製造しています。
 
オゾン水
気体であるオゾンを水に溶け込ませた「オゾン水」は殺菌や脱臭に素晴らしい威力を発揮します。
また食品の鮮度保持、農薬分解作用などもあるため、オゾン水による洗浄も食品加工では多く導入されています。
オゾン水は、水に空気中の酸素から生成したオゾンを溶け込ませて作るので添加物がなく、オゾンは消耗されるか
時間がたつと酸素に戻るかしてしまうため残留性もないため、安全・無公害であり、肌を荒らすこともないため、
口に入れるものの洗浄殺菌から手洗い、うがい用水まで安心して使用できます。
またニオイの元になる有機物 や微生物をオゾンが酸化分解するので、殺菌と脱臭を同時に行うことができます。
オゾン水の導入メリット

非加熱処理をする食品(カット野菜、鮮魚など)は、従来、薬品処理をしていましたが、オゾン水に置き換えることで
薬剤に頼らない、エコで安全な洗浄システムにできます。
また 配管洗浄や什器洗浄にオゾン水を使うと、汚れが蓄積しにくくなるためメンテの時間と手間を減らせます。
さらに日常の清掃にオゾン水を利用すれば、床から舞い上がる浮遊菌がなくなり、オゾン水の脱臭効果で、
臭いや油汚れも軽減されていき、クリーンな衛生環境作りにも有効です。
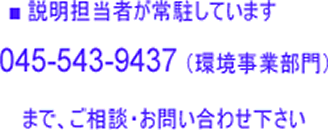
 メール catch@m-n-w.com メール catch@m-n-w.com
 
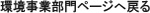
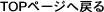 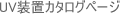
|
![]()
![]()
![]()